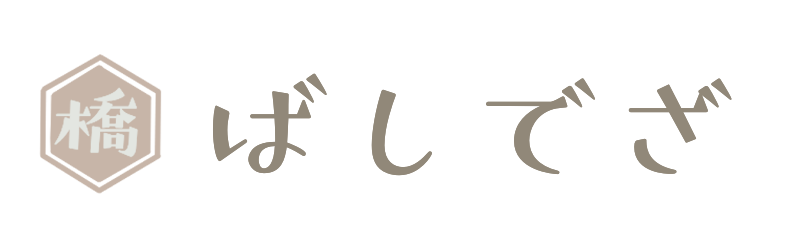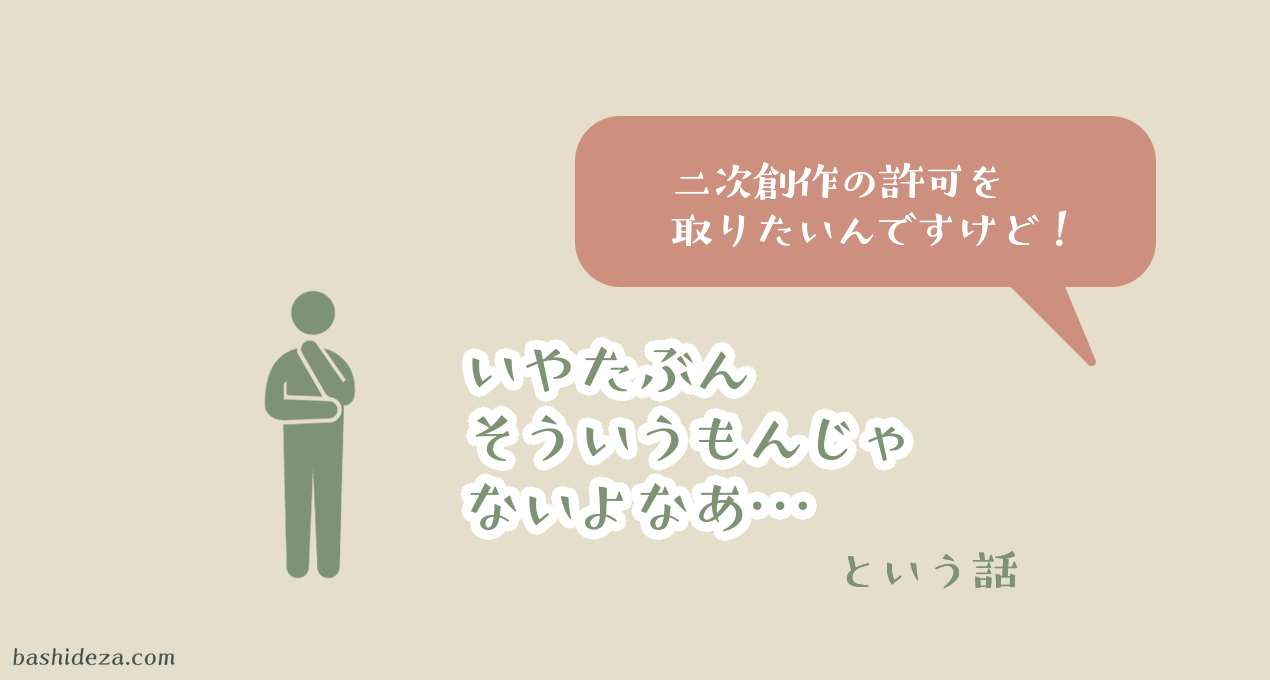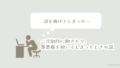よな、たぶん……。という話。

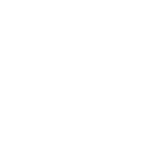
二次創作をしたいんだけど、私のジャンルってガイドラインとか出てないんだよね……出版社や作者に許可を取りたいんだけど、どうやって許可を取ればいいの?
という人向け【出版社や作者に許可を求めたら二次創作ができなくなってしまうおそれがあるし、二次創作ってそういう性質のものではないんじゃないか】という話。
※うちのブログに「二次創作 許可 取り方」で検索してくる方が多いので、こんな記事を書いてみました。あくまでも、ひとりのオタクとして考えてみたという話です。
内輪でこっそりやっていたからこそ、黙認されていた
自分も20年以上同人をやってきているけど、少なくとも以前は「黙認されつつこっそり本を作って同志で交換して、あくまでも内輪だけで楽しむ」というものだった。
ごく内輪だけだから、大々的に世間に向けてキャラクターのイメージを貶めることもなかったし、著作権者の利益をおびやかすこともなかった。だからこそファン活動の範囲として黙認されていたと言える。
(黙認=容認、ではない。本当は認めていないけど知らないふり・見ていないふり・気づいていないふりをしてくれている、みたいなことも含みます。)
SNSの普及によってそこらへんが変わってきて、
「そんなのいやだ。悪いことしてるみたいに黙ってコソコソしたくない。モヤモヤするからはっきり『いいよ』って許可がほしい。正々堂々と二次創作したい。全てのジャンルでガイドラインを出すべき」みたいに言うような人も、ちらほらお見かけする。
自分が真っ白でいたいっていうその気持ちは分からないでもないけど、たぶん、権利の問題ってそんなに白黒はっきりできることばかりではないんだよな……と、いにしえの部類のオタクとしては思っている。
むりやり許可を求めることで、全面禁止にもなり得る
むりやり許可を求めることで、先方にも、他のジャンル民にも迷惑がかかることもある。
もし「二次創作してもいいですか?」と聞いて「(立場上)ダメ(って言うしかない)です」と言われたら、公式から正式に「NO」が出たということになってしまう。
今までこっそりと著作権者に迷惑をかけないよう気をつけて創作していたジャンル民も、その瞬間から二次創作ができなくなってしまう。
「ファンの活動を規制するものではない」
出版社系はたいてい公式サイトに「著作物をもとにしてどうにかこうにかするのは禁止です」という旨のことをはっきりと書いている。
たとえば、小学館の公式サイトにもこう明文化されている。
以下のような行為を無断ですることは禁じられています。
出版物やサイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画・小説等を翻案作成して掲載・頒布すること。
小学館公式サイト 画像使用・著作権
文面だけで判断すれば「二次創作も禁止されている」ということに受け取れる。
でもこれは悪質な業者への対策なのであり、ファンの活動を規制するためのものではないというようなことを、ゲッサン編集部の公式Twitterで言っている。
おおぜいで問い合わせると業務の妨げにもなる
メールなどの手段があると、軽〜い気持ちでなんでもかんでも聞けてしまう。
「同人誌作ってもいいですか?」「缶バッジってこれなら違反にならないですか?」「キャラの服を変えるのは違反ですか?」「性的な表現はどこまでOKですか?」「自作のキャラ絵をTwitterに載せてもいいですか?」「二次創作絵を地元のお祭りのポスターに使っても良いですか?」……こんな何百件受け答えしても一銭にもならないような問い合わせが殺到したら業務に差し障りがある。
最近ではメールフォームを置かずに全部電話にしている出版社もある。それを「○○(出版社名)は電話でしか問い合わせできなくて不便、しかも電話料金はこっち持ちになるし。サービスが悪い」と言ってる人がいてびっくりしてしまった……。
ノリで何かする前に、いったん考えてみたい
今はTwitterというツールもあるので、著作権者ご本人がノリノリで「俺(たち)の作品はバンバン二次創作していいよ」「自分の作品の同人誌を喜び勇んで買いに行ったことある」「自分も二次創作してたからその楽しさは分かる」みたいに表明している人もいる。
むしろ「二次創作を禁止する方が時代的に遅れてるぅ」みたいな、なんというか、圧的な空気さえ感じることもある。
だから自分のジャンルでもつい著作者に味方になってほしくて「二次創作していいですか?(いいですよね?)」と許可を得たくなってしまうのかもしれない。
その前にいったん、あらゆる可能性を考えてみる想像力は必要な気がする。
- 「立場上、二次創作はダメとしか言えない」ということもある
- 問い合わせることで先方の業務の邪魔になることもある
- そもそも、二次創作されたくない著作権者もいる
つまり、良識・常識の範囲内で"うまくやる"しかない。
「その常識の範囲が分からなくて不安だから問い合わせたいんだよ!」みたいに、自分で判断する自信がないならば二次創作をしない。(もしくは少数の鍵アカウントにするなど、責任が取れる範囲にとどめる。)
自分も二次創作をするからこそ思うことなのだけど、「人様のキャラを使って創作をするのに自分はまったく潔白でいよう」なんて、それもムシが良い話なのかもしれない。
二次創作を取り巻く状況は20年前と比べてまったく違っているし、数年前と比べてもだいぶ変わった。これからもどんどん変わっていくだろう。
著作権者の権利や利益をおびやかさず、時流を鑑み、うまくやる。
そこらへんに自信がなくなったら「二次創作をしない」もしくは「ごく狭い範囲で行う」という決断もしていこうと思っている。