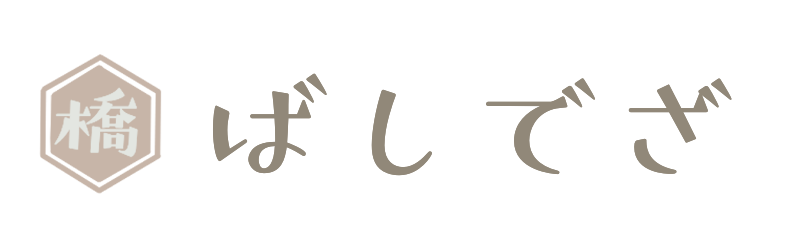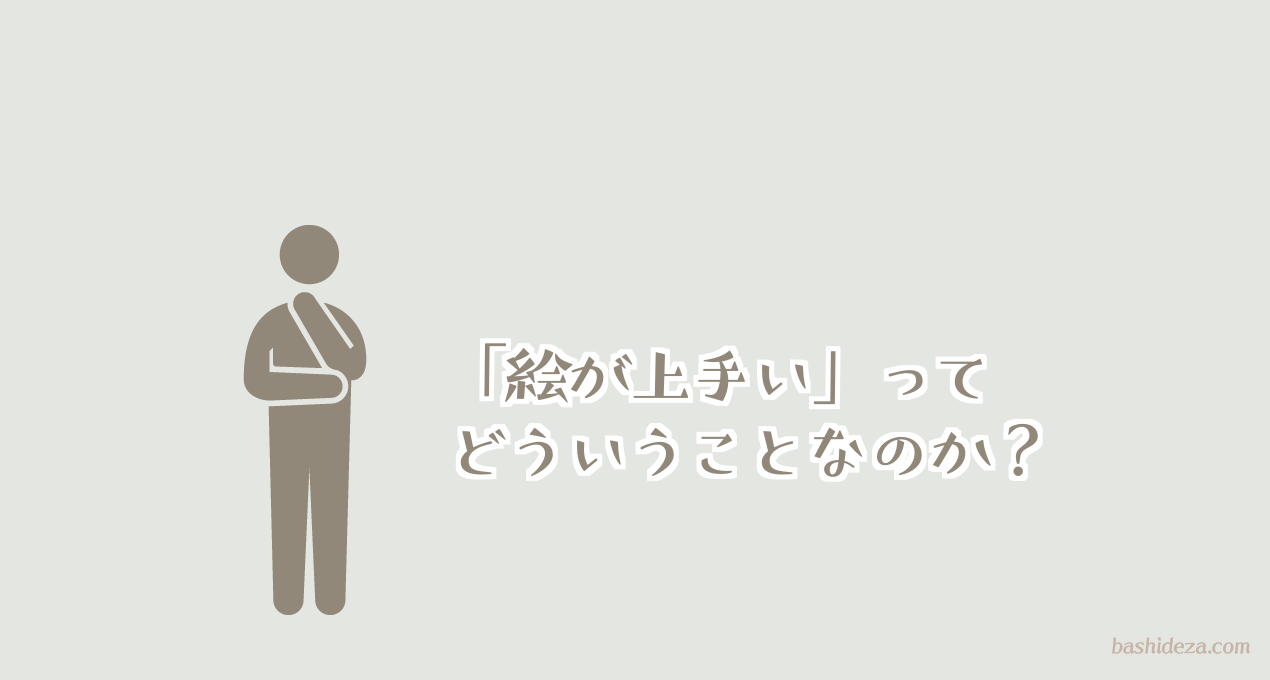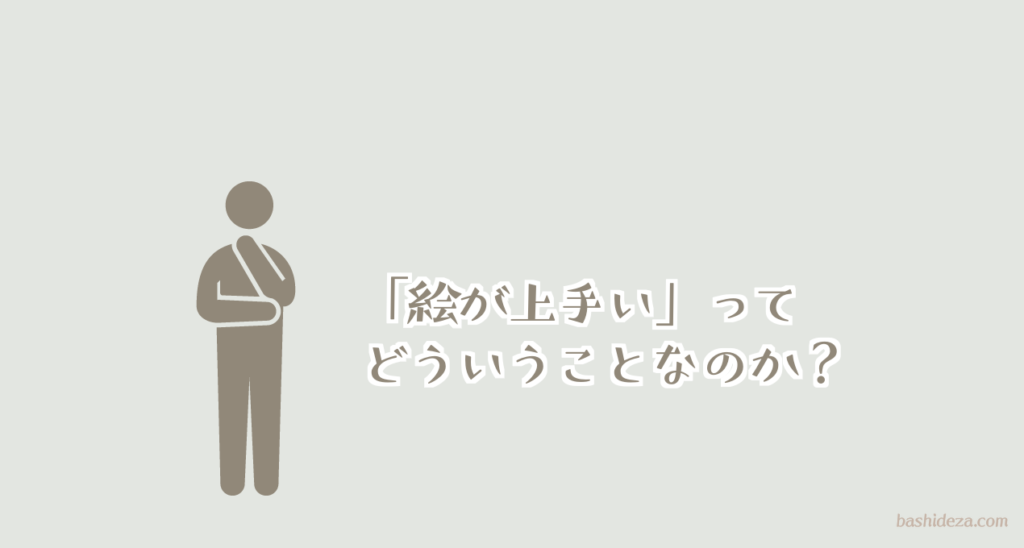
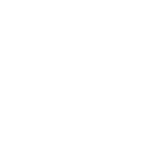
絵が上手いってどういうことなんだろう? 絵が上手いと言ってもいろいろな『上手い』があるよね……?
と疑問に感じている人向け【絵が上手いとは結局どういうことなのか考えてみたらたくさんバリエーションがあったので、自分の絵はどこを目指すのか考えてみるといいのでは】という記事。
遺跡などに当時の人が落書きした「ついなんか描いちゃった」みたいな絵が残っていることがあったりするけど、今も昔も絵って「自分の中のイマジネーションに突き動かされてつい手が描いちゃう、なんか知らないけど描きたくて描いちゃう」ものだと思うのだ。
人の中には「自分の中にあるものを表出させたい」というパッションがあるのではないかしら。排泄欲に近いような、原始的な欲求が。
だったら絵を描く上での最終目標ってつまり、「自分の中にあるイメージを、もっと思い通りに表出させたい!」ということではないだろうか。
「絵が上手い」のバリエーションいろいろ
つまり「絵が上手い」というのは自分の中にあるものをどれだけ思い通りに表出させることができるかということ。だと自分は考えているのだけど、だったらそんなの人それぞれで全く違うってことになる。
あの人の「絵が上手い」と自分の「絵が上手い」は違って当たり前。そもそも表出させたいものが違うのだから。「絵が上手い」の基準なんかないよなっていうか人それぞれで無限にあるよなってことになる。
「絵が上手くなる」には各々自分の表出のためにどんな方法を磨いたらより良いかを見極めて、せっせと磨いていくだけのこと。
流行りの絵柄が描ける
表出させたいもの:いまどきの雰囲気 の場合
「この雰囲気を描き表したい」っていうのは、絵を描いていく上でよくあるモチベーションかもしれない。その中の一つとして「いまどきの雰囲気を描き表したい」というのもあり、流行りのエッセンスがある絵柄を描けるように磨いていくことができる。
アンテナを立てて流行りの絵柄をキャッチし、おおぜいに受け入れられるイラストを描くというのはたいへんなスキルであると思う。西洋美術の歴史だって、さまざまな流行で成り立っているのだから。
主にpixivなどのイラスト系SNSでは絵柄にも流行があり、当然流行りの絵柄はたくさんのいいねを集めやすく、いわゆる「神絵師」にもなりやすい。ゆえに反発も起こるのか流行りの絵を批判する人もいるけど、それって他人が表出させたいものに対して、つまり他人の内面にケチをつけてるんだよなと考えるとかなり野暮なことだな……と今思った。
動きのある絵が描ける
表出させたいもの:キャラの動き の場合
「(ダンスなどで)ここの振り付けの手の動きがたまらなく好き、このニュアンス分かるかな〜、この、これ! 絵で伝えたい!」みたいなのって、いくら人体が正確に描けても伝えられないことがあり、むしろデフォルメしてちょいちょいっと描いた絵の方がめちゃくちゃ伝わったりする。
人体はそこまで正確に描けていなくても、伝えたかった動きのニュアンスが伝わればそれでその表現は大成功ということ。
アニメーターの方の教本などを読んでいると、動きを表現することと人体を正確にとらえることはまた別のコツというか能力が必要になるんだな、というのを感じることがある。正確に描くことより、ちょっとした誇張やデフォルメをすることで、より「それっぽく」見せる技術というか。
どちらもそれぞれの表現であって、どちらが高尚とかどちらが「上手い」とかではない。
人気マンガでよくあるパターンが、「デッサンは狂いまくってるけどアクションシーンが最高。デッサンの違和感を凌駕する」みたいなもの。ルネサンスの後期にも、【マニエリスム】という流行があり、これも現代風にいうと「骨折絵だけど表現したいことを強調させて伝える」という手法だった。
人目を引く配色ができる
表出させたいもの:色づかい の場合
「こんな色づかいで描いてみたい」というのってある。普段使わないパレットだったり、好きなトーンを集めたパレットだったり、「この色をメインで使ってこんなイメージの絵にしたい」だったり。
海外のクリエイターの作品を目にすると、自分の引き出しにない色づかいにハッとすることも多い。環境や文化、好みによって、使う色彩は意外と固定されてしまっているのかなあと感じる。
「何でその色をそこに使おうと思ったんだ!? すごい!」という感動ってある。
自分の思いや気持ちを伝えてくる
表出させたいもの:自分の思いや気持ち の場合
自分の思いとか気持ちを絵で表出させたい人もいるだろう。「絵を描く人ってみんなそうなんじゃないの?」と思われがちだけど、意外と違う気がする。「この色を使いたい」「この動きを表したい」「この雰囲気をかもしだしたい」などいろいろある中の一つとして「自分の気持ちを絵で表したい」があるというか。複合的にいろいろ混ざっていることもある。(※筆者の感覚です)
模写が正確にできる
表出させたいもの:なるべく正確にそのものを伝えたい の場合
「なるべく正確にそのものを絵にしてみたい」ということもある。果物やガラス瓶をそっくりに模写して、実物と並べたらどっちが絵か分からない、みたいなのとか、推しの顔をまるで写真みたいに模写したりとか。
「そっくりそのまま模写するのって意味あるの? 写真でいいじゃん」って言う人もいるけど(実は自分もそう思っていた時期があるけど)、その表現者は「なるべく正確にそのものを絵にしてみたい」というパッションを元に表現をしているだけの話で、意味があるとかないとかそういうものではないんだと思う。
また「模写ができてもオリジナルが描けなきゃ意味がないよ」と言われるけど、アートの世界には【贋作師】という存在もあって、ベルトラッチという贋作画家は2000点のニセモノを描きその被害総額は45億以上だったという。しかしその絵を「上手い」「素晴らしい」と思った人が多かったからこそ、美術界を騙し続けることができたわけだ。
※当たり前だけど、他人の絵を模写して自作発言はダメです。
よく見てディテールを描ける
表出させたいもの:モノのディテール の場合
普段何かモノを見るときって、ディテールまでは見ない。カブトムシの足に生えてる毛とか、リンゴの皮のグラデーションとかなんてそうそうじっくりとは見ない。
それだけに、「このリンゴの皮のグラデーションの美しさよ!」と大発見して感激したから描いてみたい、みたいなのってある。推しの眉毛の生え方が眉頭と真ん中へんと眉尻で違うのを執拗に描き表したいんだ、と言っていた知人もいた。
それは観察力であり、見たものを写しとる表現力とも言える。
図工の時間に「よーく見て描きましょう」というふうに言われたことがあるけど、あれって「よーく見ることでそこに何を発見してどう感動してそれをいかに描き表すか、それが絵を描くってことですよ」というのを教えたかったんじゃないかなと今となっては思っている。
自分がよーく見て発見して感動して描き表したディテールが、他人の目と心を惹きつけて共感を生む。その到達点の一つが、桂正和先生の描くパンツのシワなんじゃないか。(個人的な意見です)
デフォルメ、省略ができる
表出させたいもの:簡略化した世界 の場合
これは自分もそうなのだけど「複雑な人体やらなんやらをシンプルにシンプルに、簡略化してみたい」という気持ちが強くある。自分は似顔絵を描くので「簡略化して、いかに似せるか」ということに取り組んでいる。
どれだけリアルに描こうがしょせんはどんな絵も現実のデフォルメであり、「現実を紙の上にどうやって表現するか」というのが絵描きの命題。上に挙げた「なるべく正確にそのものを伝えたい」の真逆の手法になる。
視線誘導の勘がある
表出させたいもの:空間 の場合
絵の中に空間があって、描かれたその世界を漂うように見てしまう絵ってある。何か対象物を描きたいというよりは、その空間を切り出しているような絵。
その空間を表すためには、構図だったり、モチーフの大小、空間の開け方、色選び、描き込みの粗密などで自然に見る人の視線を誘導し、大きな感動を与えるテクニックが必要になる。
これは理論を学んで覚える人もいれば、多くの作品に触れることで知らず知らず身についてしまい、感覚でできてしまう人もいるだろう。
自分の中のイメージを思い通りに表出させる
「絵が上手くなりたい」というのは漠然としすぎていて何からがんばればいいかも分かりにくい。だからつらくなったり、挫折したりもしてしまう。「あー痩せたい(けど何していいかわからない)」と似ている気がする。
だから「絵が上手くなりたい」は自分の中では長らく禁句みたいにしている。
絵を描いている人なら、自分の中から出てくる「なんか知らんけど描きたいから描いちゃうもの」って必ずあると思う。それは人と違っても全然よくて、一般的な「絵が上手い」と違っても全然よくて(もちろん上に挙げてきたどれとも違ってもよい)、それこそを大事に表出させていかないと、絵を描くのってすぐつまらなくなるんじゃないかなと思います。