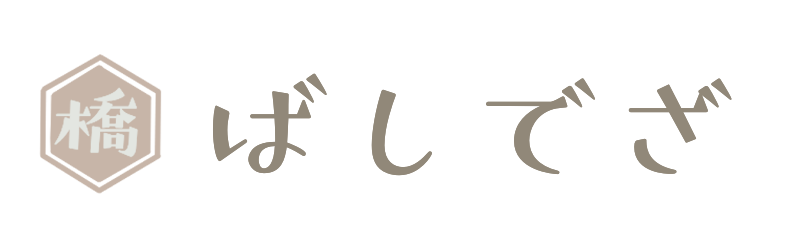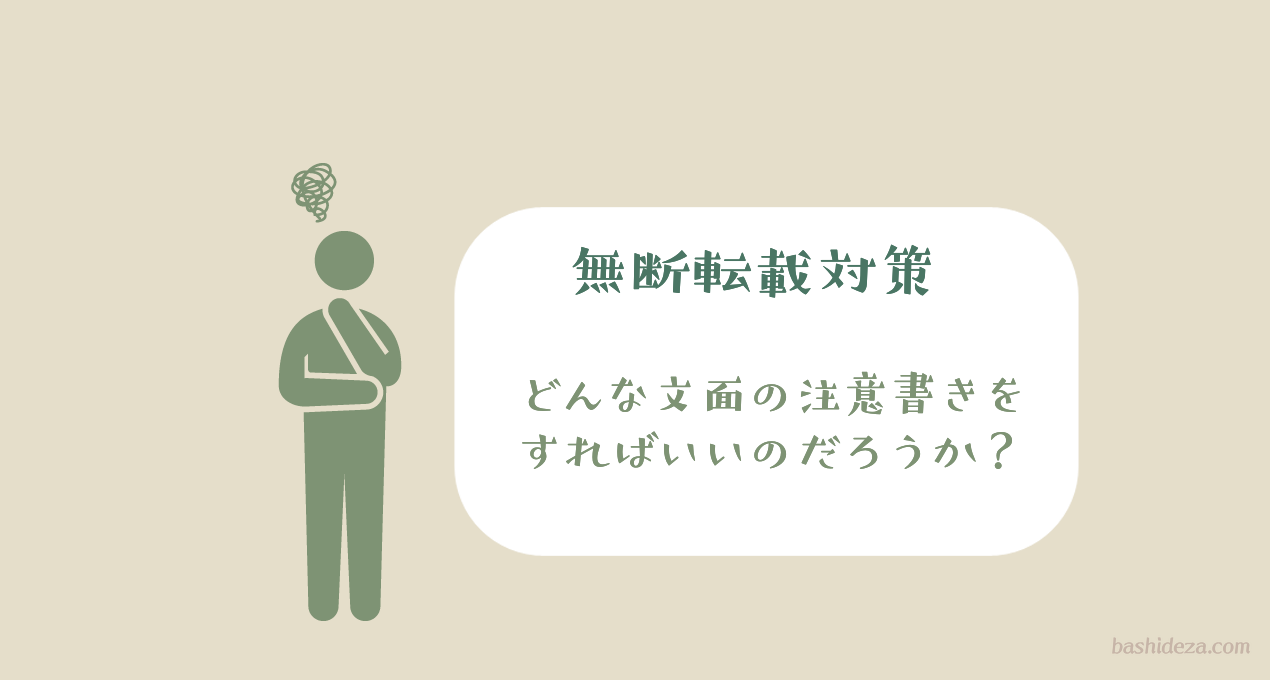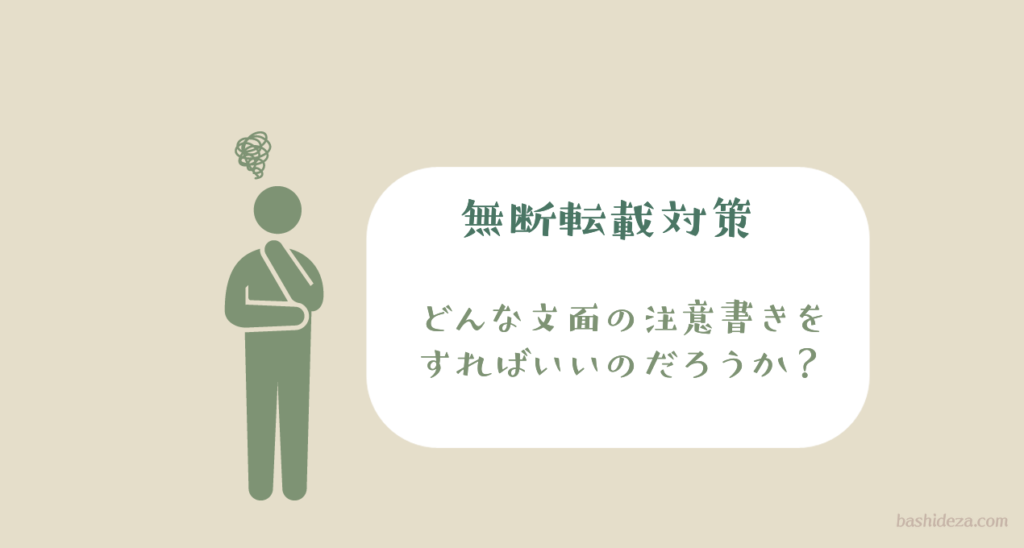
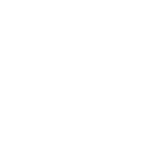
無断転載を防ぐために注意書きをしたい。効果があって、あまり角の立たない注意書きの例文ってないかな?
という人向け【角が立たないようなやさしい注意書きだと伝わりづらく、逆効果になることもあるのかも。シンプルにはっきりと、言い切りの形で書いた方が伝わりやすいかもしれません】という記事。
以前、pixivでこんな感じのコメントを見かけた。
「無断転載禁止です」と明記しているユーザーへのコメントで、
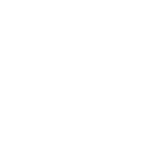
○枚目のイラスト、Twitterのアイコンに使わせてもらいました!
無断転載禁止だそうなので報告しますね♪ ダメなら返信下さい!
「転載はご遠慮ください」と明記しているユーザーへのコメントで、
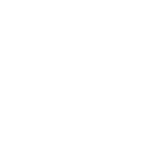
上手い絵なんだから、遠慮なんかしなくていいんですよー♪
Twitterのトプ画に使わせてもらいますー!
「無断転載禁止」とか「転載はご遠慮ください」では、相手によっては意味が伝わらないこともあるんだな、ということを感じた。
自分も絵を描くので一応SNSのプロフィールに「無断転載禁止でお願いします」みたいにふわっと注意書きを書いて「よし、これでまあ安心だろう」と思っていたのだけど、これではきちんと伝わっていないかもしれないんだなと。
※以前オリジナルを描いていた頃はあまり考えていなかったけど、二次創作をするようになってから、転載されることで自分以外に迷惑がかかることがあり得るので気にするようになりました。自分の絵をたくさんの人に見てもらうことよりも、権利者に迷惑をかけないことを最優先にしたいと思ったからです。
もう少し多くの人に伝わりやすくするためには、どんな文面にすればいいのか考えてみた。
「転載禁止」を分かりやすく伝える注意書きを考える
ネットにはいろいろな考え方の人がいて、「あなたの絵を好意で拡散してあげている」という考えの人もいれば「いいものは共有したいから転載しているだけ」という人もいる。著作権とか複製権についても、人によって認識も解釈も違う。
なので、転載されたくないならば「私の絵は転載しないで」と作者が意思表示をしておくことが重要になるのだと思う。
シンプルな言葉で
上に挙げたpixivのコメントを見て自分が考えたのは、「シンプルな言葉でキッパリと注意書きをしておくほうがいいのかもな」ということだった。
画像の転載、複製、改変等は禁止します
画像の転載、複製、改変等はいかなる場合も禁止
「無断転載は〜」と書いてしまうと「無断じゃなきゃいいんでしょ? じゃあ許可をください」「無断はダメでもコメントで報告したから使っていいよね?」という人が少なからずいるのだと思う。
確かにそういう解釈もできてしまうし、もし「無断がダメなら転載の許可をください」と言われても自分は転載の許可はしたくないので、最初から「無断で〜」などは書かずシンプルに「転載禁止」と書くことにした。
考えてみれば、自分は無断だろうが無断でなかろうが転載はされたくないという考え方なのに「無断で〜」は要らなかったなと。いらぬ誤解を招く書き方になっていたなと。
また、「転載はやめてくださいね」「ご遠慮ください」みたいな優しい文面だと「頼んだら許してくれそう」「しても怒られないだろう」と思われてしまうのかもしれないな、と感じたし、さらに「ご遠慮ください」だと意味が通じない人もいるという新しい可能性にも気付いた。
今まではつい、「私ごときの絵を転載する人なんていないだろうし、あんまりきつい言い方で書くのも申し訳ないというか自意識過剰っぽいかな……」と思ってしまってごくやんわり、ふわっと書いていたのだけど、却って伝わりにくくて不親切だったということになる。
人は長い注意書きは読まないので、短い言葉でプロフィール欄のいちばん先頭に記すというのも大切なのかもしれない。
- 「無断じゃなきゃいいんでしょ?」とも受け取れるので「無断で〜」は書かない
- 角の立たない言い回しにしすぎると伝わりにくくなるので、言い切りの形で
- 長い注意書きは読まれにくいので、プロフィールの先頭に短い言葉で
ジャンルや界隈のユーザー層に応じて、かみくだいた言い方にする
そもそも「転載って何?」という人もけっこう見かける。
「収入を得なければ転載にならないんでしょ?」「誰かの絵を自分のTwitterのアイコンにするくらいなら転載じゃないよね?」「誰々さんの絵ですって書けば転載しても転載じゃないよね?」「加工してポエムを書き込めば私の作品ってことになるよね?」←? みたいな人々を実際に目にしたことがある。(いずれも転載にあたります)
もしネットリテラシーの低い人やSNS歴の浅い人が多いジャンルならば、
私の絵をアイコン、ヘッダーなどに使用しないで下さい。
私の絵を保存してTwitterなどに投稿しないで下さい。フォロワーにおすすめしてくださる場合は、RTでお願いします。
などとかみくだいた言い方にすると、少しは伝わるのかもしれない。
あとは、人の絵を転載して自分の絵だといつわる人(「誰かの絵にポエムを書き込めば私の作品ってことになるんでしょ?」のような人)も少なからずいるので、
転載、複製、加工、及び自作発言を禁止します
私の絵にポエムを書き込んで自分の作品として投稿しないでください。
などとかみくだいた言い方にすると、少しは伝わるのかもしれない。
英語でも注意書きを
また、SNSはいろいろな国の人が見られる場だから、少なくとも英語でも注意書きをしておきたい。転載されてから英語で注意したり削除を求めたりするのは、英語が苦手な人にとってはもっと骨が折れるからだ。
面倒は未然に防ぎたい
今は誰もが気軽にSNSを始められるせいなのか、著作権の知識がない人に悪気なく転載されてしまうことがある。
ネットに「落ちてた」いい感じのイラストを「拾って」使っている、みたいな感覚なのかもしれない。
注意すると「え、これって転載になるんですか? 知らなかった、ごめんなさい」とすぐに消してくれる人もいれば、泥棒呼ばわりされたと感じて「転載されたくないならネットにアップするな!」「たかが絵を描けるくらいで偉そうに言うな!」と逆ギレしてくる人もいる。見知らぬ人とのいざこざで、心がすり減るような経験をした絵描きのかたも多いだろうと思う。
少しでも面倒に巻き込まれにくくするためには、なるべく伝わりやすい注意書きを入れておくと"少しは"お互いのためにいいのかなと感じる。
また、併せてイラストにサイン(SNSのIDやURL)を入れておくのも"ある程度は"転載を防ぐ効果があると思うので、自分はやってみています。
- 分かりやすい、シンプルな、ジャンルの層に合わせた注意書き
- 英語でも注意書き
- サイン(IDや URL)を入れる
Twitterよりも転載対策が考慮されているSNSやサービスもいくつかあるので、「転載されすぎて疲れてしまった……」という人は他のSNSやサービスを併用するのもいいかもしれない。