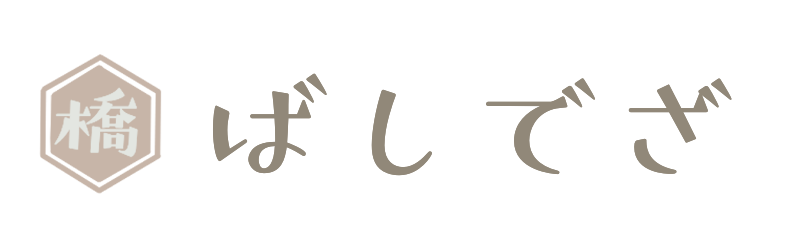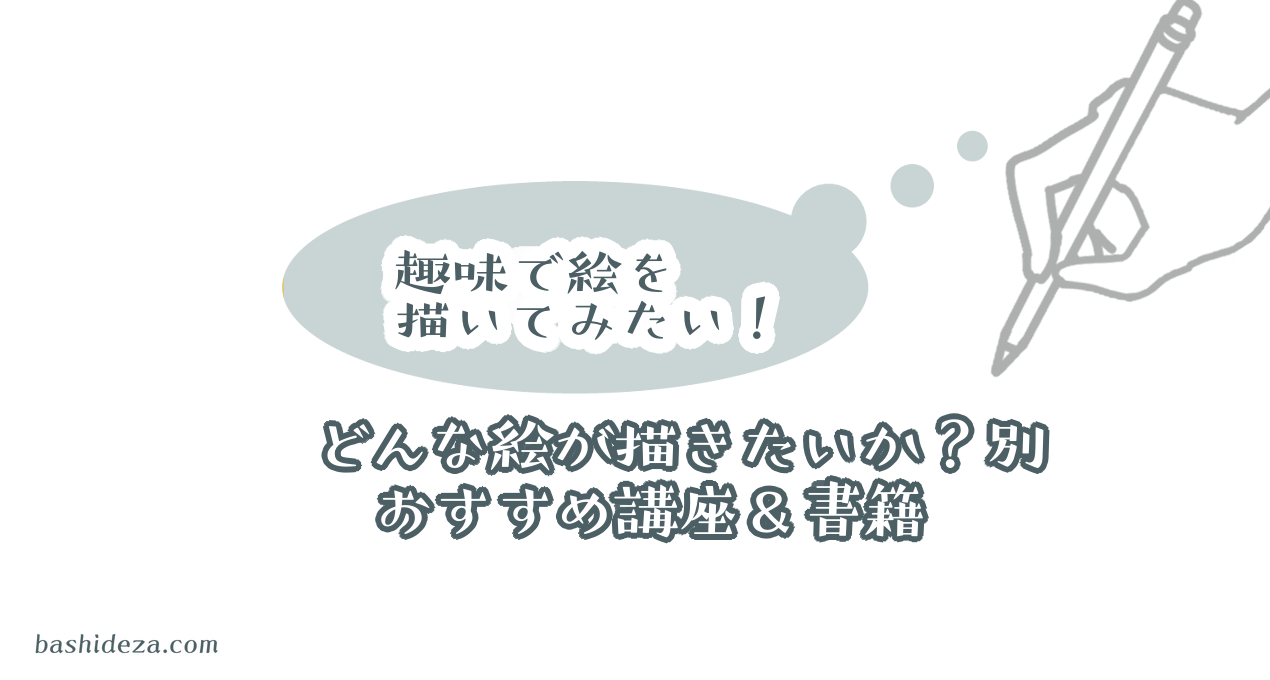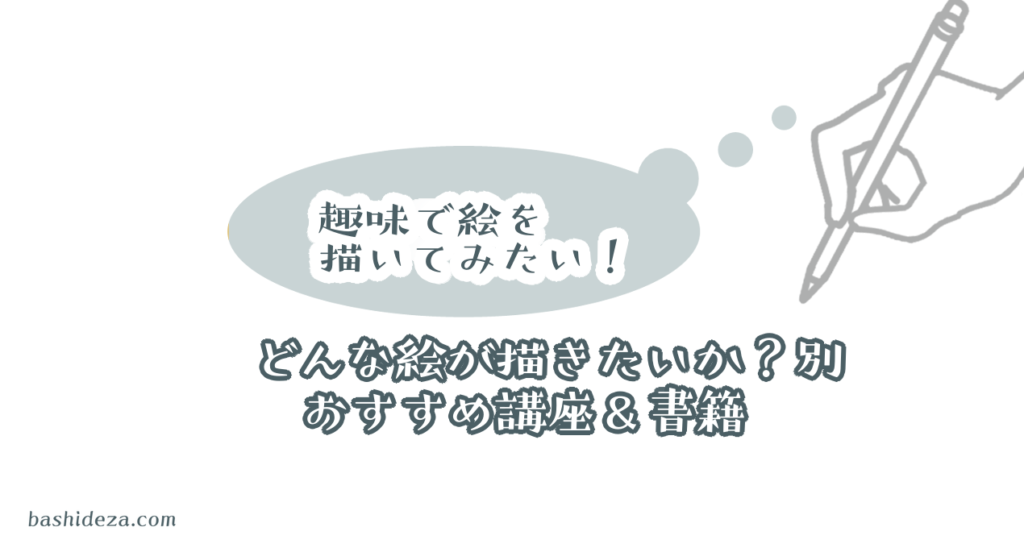
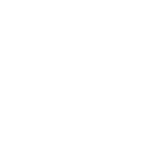
全くの初心者だけど、イラストを趣味で描いてみたい。
でも何から始めたらいいのか分からないな……
という人向け、【どんな絵を描きたいか①リアルタッチの鉛筆画②マンガやアニメっぽいイラスト③スケッチっぽいリアル寄りの絵④手帳に描いたりできるかわいい系のイラスト、などジャンル別のおすすめ講座やおすすめ書籍】についての記事。
「趣味で絵を始めてみたい」という方の話をけっこう聞くのだけど、どんな絵が描きたいのか聞くと「うーん、それは分からないけど、絵を描けたらいいなと思って。とにかく趣味で絵を描いてみたい」などと返ってくることが多い。
これだと手をつけようがなくていつまで経っても始められないので、「自分がどんな絵を描いて、描いたその絵をどうしたいのか」ということまで思い描いてみると、取っ掛かりがハッキリしやすいかもしれない。
「SNS映えする絵を描いて、Twitterに投稿してみたい。いいねがついたらいいな」
「推しの誕生日にファンアートを描いてプレゼントしたい」
「好きな作品の二次創作を読みまくって、自分も描いてみたくなった」
「手帳にかわいいイラストを描いてみたい。後から見返して楽しい手帳にしたい」
同じ「絵を描きたい」でもそれぞれ取っ掛かりが違うので、それぞれの描きたいものにマッチした参考書籍やオンラインの講座を挙げていく記事です。
SNS映えするリアルタッチの色鉛筆画を描いてみたい
SNSでリアルタッチの鉛筆画を見かけると「おっ! なんだこれ! すごい絵だ!」と目が留まったりする。
リアルタッチの鉛筆画ってすごい特技な感じがするけど、実は少し練習するだけでもそれっぽい目を惹く絵が描けるようになる。もしかしたら一発目からそれっぽい上手いっぽい仕上がりになっちゃうかもしれない。
自分も初心者の頃にリアルタッチの鉛筆画を描くのにハマっていたのだけど、自分ではアラが見えないので書いていて楽しいし、他人からも「上手い!」「すごい!」と褒めてもらいやすいのでよけい楽しかった記憶がある。
絵ってデフォルメすることのほうが却ってセンスや技術が必要になったりして難しかったりするので、リアルタッチの鉛筆画って、意外と初心者ほどとっつきやすいと言えるかもしれない。
『写真みたいな絵が描ける色鉛筆画』
「絵を描く」というよりは「写真を絵で再現する技術」。
「自分でゼロから描きたいわけじゃないけど、とにかく絵を描いてみたい」というニーズに合う手法かもしれない。
すごすぎて最初から全部真似するのは無理だけど、掲載されている詳しい過程を見るだけもワクワクするし「自分なりに」取り入れて楽しめる。
『色鉛筆画ワークブック』
絵の描き方というよりは、色鉛筆で陰影をつけたり立体感を出す手法など塗り方のコツについての書籍。ドリル形式で直接描き込める形式だけど、紙質にこだわる人は描き込む使い方ではなく参考書籍として。
どちらもプロ仕様の色鉛筆を使っているので、「手持ちの安い色鉛筆だと混色の具合など完全に再現できなくてストレスを感じる」という人も。しかしなかなかこれは道具だけの問題とも言い切れないので、「初心者なりに手持ちのもので、今自分ができる範囲でプロの技を真似してみる」というのを楽しむ使い方をするほうがストレスがないかもしれない。
※初心者歴30年の自分としては、すごい技術は全部真似しようと思わずに「へえ〜! すごい!!」と、とりあえずワクワクとして受け止めておくのが最大のコツな気がします。
マンガ絵やアニメ絵を描いてみたい
マンガ絵やアニメ絵を描いてみたいという場合、pixivが運営している『sensei』という動画の講座がある。

動画でイラストのコツを学びながら自分でも描いてみる、という流れで、一本の動画も3分ほど。
マンガ絵やアニメ絵ってデフォルメされていて、そのまま模写するとかだと上手くなるまでちょっと遠回りになりがち。その点『sensei』は人体の基本構造を簡単にかいつまんで学べるのがすごくいいと感じる。シンプルで簡単なところからじょじょに教えてくれるので、初心者ほどいいと思う。
全くのゼロから絵を始めた友人は「『sensei』楽しい! 毎回へえ〜ってなるよ!」と言って着々と上達していった。初心者でなくとも、素直に教わる気持ちを持つ人は楽しんで身にできそう。
※自分の場合「言っても私は初心者じゃないから……」みたいな中途半端なプライドが悪く出てしまい、「こんな簡単なのやってられない」とおごりが出がちで投げ出してしまった。反面教師としてみてください。
入門編は無料なので気軽に始められます。(実践編はpixivプレミアム会員登録が必要)
アニメ絵やマンガ絵の教本は多いので、描いていくうちに、より自分の好みのテイストを絞っていくといいのかも。
スケッチっぽいリアル寄りの人物画を描いてみたい
逆に「リアル寄りの人物を描きたいから、アニメっぽい絵以外の参考書籍がほしいんだけど……」というのもよく聞く。
リアル寄りの人物を描く参考として、自分は老舗の個人サイト『人を描くのって楽しいね』さんにお世話になった。
15年以上前から人物画の描き方について教えてくれているサイトで、書籍化もされている。
「骨盤はハート形」とか「唇の構造はウインナーがつながった形」みたいな感じで骨格や筋肉の構造をシンプルに図解してくれているので、人体のうわべだけでなく美術解剖学的な学び方ができる。その分じっくりと取り組む必要はあるけど、「本格的に人物を描いてみたい!」という人にとってはモチベーションが上がるサイトだと思う。
※自分は初心者10年目くらいの「人体の構造をきちんと把握したい」と感じていた頃に出会って、たいへんお世話になったサイトです。
書籍ではサイトの情報がより補完されており、『顔・頭編』『衣服編』も。(サイトの作例は人体の全身メインなので、頭部と衣服に特化されたシリーズはありがたかったです)
かわいい系のイラストを手帳に描きたい
「本格的な絵の練習っていうより、手帳にかわいいイラストをちょっと描いたりしたいんだよね」という人もいるだろうと思う。
最近ではいろいろなテイストのかわいいイラスト教本や塗り絵で練習できる本が出ているので、真似して描いてみることができる。
また、通信販売の『フェリシモ』ではイラストの通信教育も行っている。
「習い事としてイラストを練習してみたい」という人も手軽に試せそう。
まずはどんな絵を描きたいか、描いてどうしたいかを想像してみる
この記事では、初心者でも始めやすくて興味を持ちやすいものを挙げてみたけれど、これ以外にも風景画とか抽象画とか、絵にはいろいろなジャンルがある。
特に最近はSNSで「へー、こんな絵の描き方があるんだ!」みたいなことも日々知ることができるし、表現の手法も日々増えていると感じる。さらに描いたものをグッズにしたりと、使い方も多様化している。
初心者に限らずアンテナを立てておいて、自分が「こんなふうに描いてみたい!」「描いた絵をこうしてみたい!」のようなものにたくさん出会うことで、よりモチベーションも高まりそうです。